実はこの記事、もともとは私自身が「個人事業主がいいのか、法人化した方がいいのか」と悩んだときの調べものから始まりました。
フリーランスで仕事をしていると、「そろそろ法人にした方がいいのかな?」と考えるタイミングが何度か訪れます。それは税金について考えるタイミングだったり、フリーランス仲間の友人が法人化したと聞いたときだったり……。
でも、手続きや費用、税金、信用力など、比べるべきポイントは本当にたくさんあって、調べれば調べるほど迷ってしまうんですよね。
そこで今回は、私と同じように「個人事業主がいいの?法人化する方がいいの?」と迷っている方に向けて、個人事業主と法人の違いを分野別に整理しました。
さらに、自分に合う形態を判断できるチェックリストも用意しています。
最後まで読めばきっと、あなたの“個人事業主にするべきか法人にするべきか問題”が解決するはずです。
設立の手間と費用の違い
まず気になるのは、始めるまでの手間と費用です。
個人事業主は、税務署へ「開業届」を提出するだけで始められます。無料で提出でき、申請は一日で完了します。「青色申告承認申請書」も同時提出すれば、節税効果が期待できます。
メモ:青色申告って何?
青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けて記録・保存することで、最大65万円の特別控除や家族従業員への給与を経費計上できる制度です。白色申告と比べて帳簿付けは複雑になりますが、大きな節税につながります。
なお、青色申告を行うには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、その年の3月15日までまたは開業から2か月が提出期限です。
法人は、会社の種類(株式会社、合同会社など)を決め、定款(会社の基本的なルールを定めた書類)の作成・認証、登記申請などの複数の手続きが必要です。
登録免許税(会社設立時に国に納める税金)や定款認証費用を含めると、株式会社なら最低でも約20万円が必要になります。
メモ:会社設立費用の内訳登録免許税:15万円(最低額)定款認証手数料:5万円(資本金100万円未満の場合)定款謄本代:約2,000円(通常2冊分) ※電子定款を利用すれば印紙代4万円は不要合計:約20万円~
| 項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社の場合) |
| 設立手続き | 開業届提出のみ | 定款作成・認証、登記申請など複数の手続き |
| 設立費用 | 無料 | 約20万円〜 |
| 設立までの期間 | 最短1日 | 1〜2週間 |
結論
スピード重視、または初期費用を抑えたいなら個人事業主、初期費用と時間をかけても体制を整えたい場合は法人が向いています。
会計・経費に関する違い
会計処理や経費の扱いは、事業運営の効率や節税効果に大きく影響します。
個人事業主は、青色申告か白色申告かによって帳簿付けの方法が変わりますが、簡易簿記で対応できるため、会計ソフトがあれば自分ひとりでも処理しやすいでしょう。
ただし経費として計上できる範囲は法人よりも狭く、福利厚生費は経費として認められません。
法人は、複式簿記(すべての取引を2つ以上の科目で記録する会計方法)が必須で、決算書や法人税申告書の作成が必要です。
税理士へ依頼するケースが多く、その分のコストはかかりますが、役員報酬や家族への給与、福利厚生費などを経費にできるため、節税の幅は広がります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
| 会計の方法 | 単式簿記または簡易簿記 | 複式簿記必須 |
| 申告書類 | 確定申告書 | 法人税申告書、決算書など |
| 経費の範囲 | 制限あり(家族給与・福利厚生費に制限) | 幅広く認められる |
| 会計サポート費用 | 年1万円〜3万円(会計ソフト) | 年20万円〜50万円(税理士報酬) |
結論
会計処理のコスト(時間や税理士への報酬)を抑えたいなら個人事業主、節税効果や経費活用の幅を重視するなら法人が有利です。
社会保険に関する違い
社会保険は、将来の年金額や保障内容に関わる重要な要素です。
個人事業主は、通常国民健康保険と国民年金に加入します。保険料は所得によって変動し、保障内容は基本的なものに限られます。
法人は、代表者が1人でも厚生年金と健康保険への加入が義務付けられています。保障内容は手厚くなり、将来受け取れる年金額も増えますが、保険料負担は大きくなります。
メモ:なぜ個人事業主の方が負担が軽いのか?同じく健康保険と年金を払っているのに個人事業主の方が負担が軽い理由は、保険料の計算ベースが異なるから。
厚生年金の保険料は国民年金よりも高額で設定されており、健康保険も協会けんぽの方が国民健康保険よりも高額になるケースが多くあります。
また、厚生年金には国民年金分も含まれているため、実質的な保険料は高くなります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
| 加入保険 | 国民健康保険+国民年金 | 健康保険+厚生年金 |
| 保険料負担 | 自己負担 | 会社と個人で折半 |
| 保障内容 | 基本的保障 | 手厚い保障 |
結論
保険料の負担を軽くしたいなら個人事業主、保障や将来の年金額を重視するなら法人が向いています。
信用力・資金調達・責任範囲の違い
取引先や金融機関からの信用度は、事業の継続や拡大に大きく影響します。
法人は登記や決算の情報が公開されるため透明性が高く、個人事業主よりも社会的信用を得やすい傾向があります。
また、法人は株式や社債の発行によって大規模な資金調達が可能ですが、個人事業主は自己資金や金融機関からの小規模な融資が中心です。
さらに、両者の違いとして責任範囲があります。個人事業主は「無限責任」となり、事業の負債を全額、自己の財産で返済する義務があります。
一方、法人は「有限責任」となり、出資した金額の範囲で責任を負います。この違いは、万一のときのリスクに直結します。
| 比較項目 | 個人事業主 | 会社(法人) |
| 社会的信用度 | 比較的低い | 比較的高い |
| 資金調達方法 | 小規模に限られる(株式発行不可) | 株式や社債の発行で大規模調達可能 |
| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任(出資額まで) |
結論
法人は登記や決算が公開されるため透明性が高く、信用を得やすい特徴があります。融資や契約、大規模な資金調達を視野に入れるなら、法人化の方が有利です。
法人化を検討すべき収入の目安
ここまで各分野の違いを見てきましたが、「実際のところ、いくら収入が得られるようになったら法人化を検討すべきなのか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
一般的に、年収が800万円を超えるあたりから、法人化による節税効果が顕著になります。
これは、個人事業主の所得税率が累進課税で上がっていく一方、法人税率は一定(中小企業なら年800万円以下の所得に対して15%)だからです。
さらに、法人なら役員報酬として自分に給与を支払い、給与所得控除を活用できるため、同じ収入でも税負担を軽減できます。
ただし、法人住民税(年約7万円)や税理士費用も考慮する必要があります。
あなたはどっち?個人事業主・法人チェックリスト
以下の質問に○か×で答えてみてください。○が多い方が、あなたに合っている形態です。
| 個人事業主向きチェック | 法人向きチェック |
| 初期費用をできるだけ抑えて始めたい | 安定した売上や利益が見込める |
| まず小規模に始めて、状況を見て判断したい | 大手企業や官公庁との取引予定がある |
| 事務作業はできるだけ簡単にしたい | 融資や大きな資金調達を考えている |
| 社会保険料の会社負担を避けたい | 経費の幅を広げて節税したい |
| 年間所得はそれほど高くなる見込みがない | 社会保険完備で人材採用を有利にしたい |
| 副業や小規模なサービスから始める予定 | 事業を長く続け、承継を視野に入れている |
結果の目安
- 個人事業主向きチェックに○が多い →今は個人事業主でスタートするのが現実的です。
- 法人向きチェックに○が多い →法人設立によるメリットを活かせる可能性が高いです。
- 同じくらい →専門家(税理士など)に相談しながら、将来像に合わせて検討するのがおすすめです。
個人事業主か法人か?あなたの最適解を見つけるための次のステップ
個人事業主と法人、それぞれには明確な特徴があることがお分かりいただけたでしょうか。
個人事業主が向いているのは、初期費用を抑え小規模に事業をスタートしたい方や事務作業をシンプルに済ませたい方です。
一方、法人が向いているのは、安定した収益が見込める方や、大手企業との取引、節税効果を重視する方です。
筆者自身も今回の調査を通じて、「いつ法人化するか」は事業の成長段階と将来のビジョンによって決まることを改めて実感しました。
どちらを選ぶにせよ、完璧なタイミングを待つ必要はありません。まずは今のあなたに最適な形でスタートし、事業の成長に合わせて柔軟に見直してみてはいかがでしょうか。
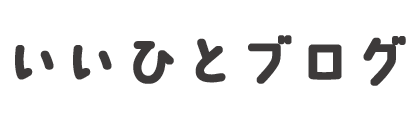
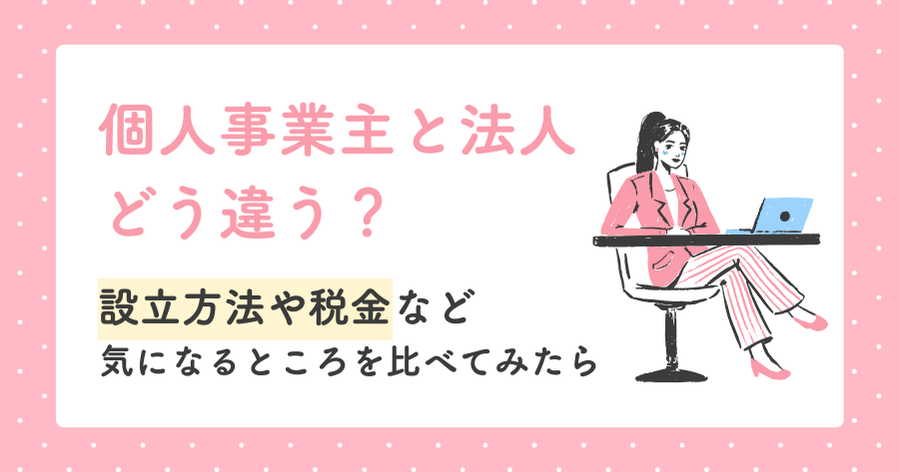
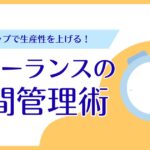



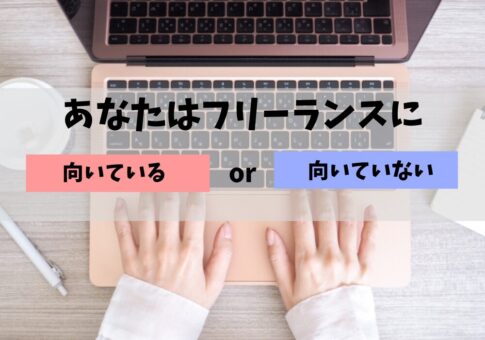

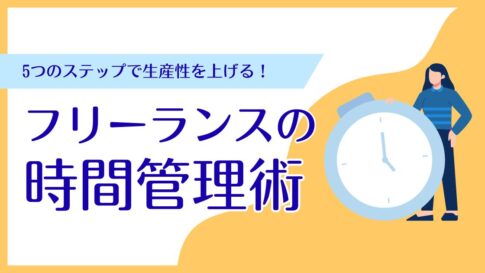
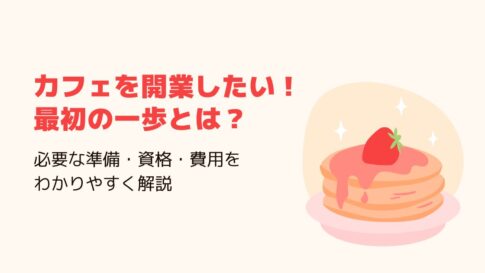













コメントを残す