みなさんこんにちは!
先日娘が3歳になりました✨
スタジオでバースデーフォトを撮影したあと、七五三プランを提案され「は!」としたのです…。
まだ何も準備していないと(笑)
そこで今回は3歳の七五三で必要な準備やスケジュール、レンタル衣装について調べてみました!
七五三の意味や由来は?
日本の伝統行事である七五三の意味や由来を調べたところ、平安時代に行われた3歳の「髪置き」、5歳の「袴着」、7歳の「帯解き」の儀式に起源があるそう。(*注釈)
当時は小さな子供の死亡率が非常に高かったため、子供が無事に育つ喜びは大きく、健やかに成長するのは今よりも困難な時代でした。
「7歳までは神のうち(神の子)」として大切に扱われ、7歳になって一人前であると認められていたそうです。
そのため3歳・5歳・7歳の節目に子供の長寿と幸福を祈願し、無事に成長したことを神様に感謝したのが、七五三の由来とされています。
ちなみに、数え年と満年齢どちらでやってもOKです。
子供の成長をみて決めるのが良いでしょう。
*注釈
「髪置(かみおき)」数え年3歳:
男女ともに行われ、それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式です。子供の成長を祝い、長寿を願う意味があります。
「袴着(はかまぎ)」数え年5歳:
男児が初めて袴を着用する儀式です。武家社会で男子が袴を着用し始める儀式が起源で、社会の一員となることを意味します。
「帯解(おびとき)」数え年7歳:
女児が紐付きの着物から、大人と同じように帯を結ぶ着物を着始める儀式です。子供の成長を祝い、大人への仲間入りを意味します。
七五三当日は何する?
一般的には、予約した美容院やフォトスタジオなどで着付けとヘアメイクを行ったあと、神社またはお寺で「ご祈祷」を受けます。
その後、予約したレストランや料亭で、家族・親族と一緒にお祝いの食事をしたり、フォトスタジオで記念撮影をしたりする場合も。
しかし小さな子供は体力・集中力が続かないので、フォトスタジオでの撮影と食事会を別日にする家庭も多いそうです。
また10・11月はシーズンで、スタジオが混雑します。
そのため前撮りを6〜9月に済ませる人や、12月ごろに後ろ倒しにする人も。
インスタで見たのですが夏は日焼けをするため、5・6月に前撮りする人も増えているそうです。
我が家は1日ですべて済ませるのが無理そうなので、ご祈祷とスタジオ撮影を別日にしようと思います。
両親が遠方に住んでいるので、食事会は要検討です。
七五三の時期は?
七五三は、一般的に11月15日に行います。
(理由が気になる人は、下記URLのサイトへ)
<参考:七五三の日は、なぜ11月15日なの?>
https://www.musashiya.co.jp/column/mamechishiki/753-1115-why/
しかし11月15日が平日で仕事の休みがとれなかったり、混雑したりするので、最近では11月15日にこだわらず、10月初旬〜12月の初旬で行う家庭が多いようです。
特に今年(2025年)の11月15日は土曜日なので、混雑しそうな予感。
我が家は寒くなる前の、10月下旬にやろうかと話しています。
ご祈祷は神社とお寺どっちがいい?
結論、神社でもお寺でもOKです。
古くからの習わしではお宮参りをした地元の神社やお寺に、ご祈祷をお願いするようです。
しかし地元で有名なところや、人気の神社・お寺へ行く人も増えています。
ちなみに、東京では明治神宮や神田明神、千葉では成田山新勝寺、埼玉では武蔵一宮氷川神社が人気です。
着物を着た状態での移動は大変なので、もし遠方の神社・お寺を視野に入れる場合、お子様の成長課程や長距離移動が可能かどうかも、見定めましょう。
ちなみに我が家は長距離移動が困難(チャイルドシートが嫌い)なので、家の近くの神社でやる予定です。
七五三の準備リスト
初めての七五三はいつ、なんの準備を始めたらいいのか迷いますよね。
ここで七五三の準備リストと、だいたいのスケジュールを紹介します。
①参拝場所・日取りを決める
早い人で11月に七五三をやろうと思った場合、3月から参拝場所・日取りの候補を決めはじめます。
いくつか候補があり、比較検討したい人は早めの準備がおすすめです。
なかには、地元の神社など参拝場所がほぼ決まっている人も。
その場合、そんなに急いでご祈祷の日取りを決める必要はありません。
9〜10月ごろから準備しても間に合うでしょう。
ある程度候補が決まったら、空き状況を電話やメールで確認するのが確実です。
②衣装を決める
まず購入かレンタルするかを決めます。
兄弟や姉妹での着用を想定する場合は、購入する人も。
しかし1人だけなら、レンタルの方が安くすみます。
レンタルの場合、直前だと衣装を選べないので、最低でも2〜3ヶ月前に準備し始めるのがおすすめです。
ちなみに、毎年だいたい3〜5月ごろに新作がでます。
トレンドの衣装を選びたい人や、多くの選択肢から最適な衣装を選びたい人は、早めにチェックしてください。
③撮影スタジオを決める
記念フォトは前撮り・当日・後撮りの、3パターンあります。
日焼けを避けたい人は、だいたい3〜6月に前撮りをするそうです。
着付け・写真撮影のセットプランがあるフォトスタジオもあり、参拝・記念撮影を当日に済ませる人もいます。
また、七五三の参拝日が終わった12月ごろに後撮りをする人も。
前撮りを検討する場合、余裕をもって年明けからスタジオの候補を探し始めましょう。
スタジオによっては、早割特典で値段が安くなります。
10〜11月のピークかつ土日はどこのスタジオも混雑するので、当日撮影なら3〜4ヶ月前(6〜9月ごろ)に予約をするのがおすすめです。
忙しくてスタジオの予約がとれなかった場合、後撮りをするのもあり。
ちなみに我が家は、前撮りシーズンを逃し、当日は参拝で疲れてしまうと思うので、12月に後撮りをする予定です。
④レストランやホテルを決める
参拝や記念撮影が終わったあと、レストランやホテルでお祝いの食事会を開催する家庭もあります。
予約は余裕をもって、1〜2ヶ月前にするのが安心。
オードブルやデリバリーを頼んで、自宅でお祝いするパターンもありです。
ただ食事会を開催する決まりはなく、やらないというのもひとつの手。
家族とよく話し合って決めましょう。
七五三当日あったら便利なもの
移動や着付けを含めると半日〜1日がかりになりそうで、当日は結構ハードなスケジュールになりそうです。
そこで先輩ママ・パパが、七五三当日に「これがあって助かった」と教えてくれた便利グッズを紹介します。
持ち物リスト
・お菓子(手が汚れず簡単につまめるもの)
・おもちゃ・絵本・シール
・スマホ・デジタルカメラ、ビデオカメラ
・ストローもしくはストローキャップ
・履き慣れた靴と靴下
・軽めのアウター(寒さ対策)
・タオル
・ヘアピン
・レインコートや折りたたみ傘
・着替え
・ビニール袋
・パッカブルトートなどコンパクトに折りたためるバッグ
・ウエットティッシュ
これらを持参するとなると、結構な大荷物。
しかし、どれもあって損はないと思います。
取捨選択して、当日の持ち物リストを作成してみてください。
気になる着物レンタルショップを調査してみた
我が家は着物をレンタルする予定です。
王道から個性派までバリエーションがあって、選ぶのに迷います。
いくつか調べているなかで、気になったレンタルショップを3つピックアップしてみました。
七五三の衣装選びで迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
①RENCA(レンカ)

(画像:レンカHP)
株式会社RENCAが運営する「RENCA」は、厳選されたネットレンタル専門店が集まる総合レンタルサイト。
アウトレットレンタル商品は4,800円からレンタルでき、私がリサーチしたなかで最安値です。
種類が豊富で、写真で見る限り安っぽさはありません。
しかも著しく汚してしまったり破損させてしまった場合でも、修理代の請求がない「安心パック」込み!
コスパ重視で選びたい人におすすめです。
②京都かしいしょう

(画像:京都かしいしょうHP)
王道・ナチュラル・ヴィンテージなど、とにかくデザインバリエーションが豊富。
こだわりが強い子でも、お気に入りがきっと見つかります。
お値段がわりとリーズナブルで、楽天にもショップがあり、楽天ポイントを貯められるのが私的にgood!(ポイント貯めてるので)
しかも七五三の衣装なら、足袋や髪飾りがついたフルセットでレンタルできるので、用意するものはほとんどありません。
私は着物を着ようか迷っているのですが、訪問着や色無地も一緒にレンタルでるのも嬉しいポイント。
ちなみに私の第一候補です!
HP:https://kyoto-kashiisyo.jp/
楽天:https://www.rakuten.co.jp/k-bridal/
③Coco bebe kimono design works
アンティーク調のデザインや、個性派衣装を探している人にイチオシ。
オリジナルの着物オーダーも受け付けています。
私は娘なので女の子の衣装ばっかり見ていましたが、ここは男の子の衣装も他にはないテイストでとってもおしゃれです。
人と被りにくい衣装を探している人は、ぜひチェックしてみてください。
HP:https://cocobebe.base.shop/
Instagram:https://www.instagram.com/cocobebe_m
一生に一度の特別な日に素敵な思い出を
七五三は一生に一度しかない、本人にとっても家族にとっても特別な日です。
今回調べてみて、早めの準備が大切なんだとわかりました。
我が家はだいたいの候補はあるのですが、本格的な決定はこれから。
そろそろ本腰を入れて準備し始めます!
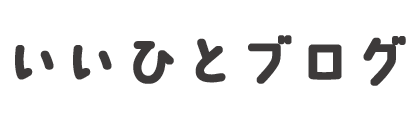










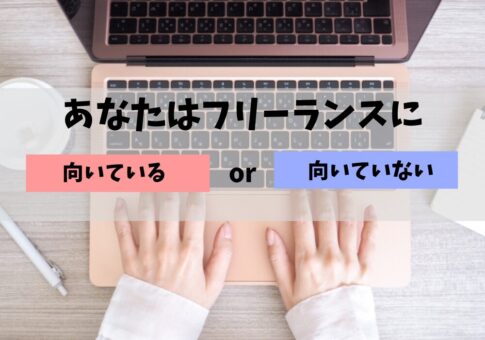











コメントを残す