「自分のお店を持ちたい」という夢はあっても、いざ実際に動こうとすると「何から始めたらいいのか分からない」と立ち止まってしまう方も多いはずです。
特にカフェは人気の業態で、雑誌やSNSで素敵なお店を見かけるたびに憧れが強くなる一方、「資金はどのくらい必要?資格はいるの?」といった疑問も膨らむでしょう。
そこで本記事では、「起業シリーズ」第一弾としてカフェの開業をテーマに取り上げます。このシリーズは、起業を夢見る方と同じ目線に立ち、「一歩を踏み出すために必要なこと」をご紹介していきます。
この記事を読めば、
- カフェ開業を考えたらまず取り組むべきこと
- カフェ開業に必要な資格や手続き
- 費用の目安や小さく始める方法
といった全体像がつかめます。漠然とした夢が現実に近づき、「次に自分がやるべきこと」が見えるようになるはずです。
▼その他の起業シリーズはこちら
居酒屋開業の第一歩|理想のお店を形にする準備と費用
自分の雑貨屋を開きたい!開業に必要な準備・資格・費用をやさしく解説
カフェ開業を考え始めたら、まずやること
カフェを始めたいと考えたとき、最初のステップは「お店のイメージ」と「なぜ開業したいのか」という動機をはっきりさせることです。
ここが曖昧なままだと、物件探しやメニュー開発、資金計画など、各段階で迷いが生じ、勢いが失速する原因になりがちです。
コンセプトを整理してみる
まずは、どんなカフェにしたいかを言葉にすることから始めましょう。
紙に書き出すのでも、パソコンでまとめるのでも構いません。
「落ち着いた雰囲気で本が読めるカフェにしたい」「仕事帰りにさっと寄れるコーヒースタンドにしたい」といったように、イメージを具体的にすることが大切です。
整理のコツは「5W2H(When/Where/Who/What/Why/How/How much)」を使うこと。
- どの時間帯に利用してほしいか
- 誰に来てほしいか
- どんな体験を提供したいか
こうした視点で考えると、頭の中のアイデアがぐっと現実的になります。
簡単な事業計画にまとめてみる
コンセプトや想いを形にする次のステップは、簡単な事業計画を作ってみることです。
融資を受ける予定がなくても、計画書を持つことで「内装や看板の方向性」「メニュー構成」「集客方法」を決めやすくなり、経営者としての自信にもつながります。
他店から学び、自分の強みを見つける
気になるカフェに足を運び、どんなお客さんがいて、何が魅力的なのかを観察してみましょう。
その上で、自分ならどんな強みを出せるかを考えることが、他店との差別化につながります。
大手チェーンにはできない、自分だけの特徴を探すことが重要です。
カフェを始めるのに必要な資格・手続き
カフェを開業するには、法律や安全面に関わる資格や許可をそろえる必要があります。
ここでは、必ず取得が必要なものから条件次第で必要になるものまでご紹介します。
必ず必要なもの
まずは「どんなカフェでも必ず必要になる資格・許可」です。
- 食品衛生責任者
店舗ごとに1名は必ず配置が必要です。各都道府県の食品衛生協会が実施する1日の講習(約6時間)を受ければ取得できます。調理師や栄養士などの国家資格がある場合は講習免除のケースもあります。
参考:一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者会場集合型養成講習会」 - 飲食店営業許可
すべての飲食店に必須の許可です。保健所に申請し、内装工事後に検査を受けて基準を満たせば交付されます。取得まで数週間を見込んでおきましょう。
参考:厚生労働省「食品衛生申請等システム」
この2つを押さえることが、カフェ開業の大前提になります。
条件によって必要になるもの
次に「お店の規模や提供内容によって必要になる資格・許可」です。
- 防火管理者
収容人数が30人を超える場合に必要です。消防署などで講習を受けて取得します。乙種は1日(約5時間)、甲種は2日(約10時間)が目安です。
参考:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」 - 菓子製造業許可
ケーキやパン、焼き菓子などを製造して販売する場合に必要です。保健所に申請し、施設検査を受けて許可されます。取得まで数週間かかることが多いです。
参考:東京都保健医療局 食品衛生の窓「営業許可種類一覧」 - 深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜0時以降にアルコールを提供する場合に必要です。営業開始の10日前までに警察署へ書類を提出します。
参考:警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)」
どれも条件次第で必要になるものなので、開業形態が決まったら必ず確認しておきましょう。
開業に関する届け出
さらに「事業を始めるうえで税務上必要な届け出」もあります。
- 開業届
個人事業主として開業する場合、開業から1か月以内に税務署へ提出します。
参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 - 青色申告承認申請書
確定申告で控除を受けたい場合、開業届と一緒に提出しておくと安心です。
参考:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
税務署への届け出は、スムーズに確定申告を行うための重要な準備です。
必須ではないが役立つ資格
最後に「必須ではないけれど経営に役立つ資格」を紹介します。
- 調理師免許
食品衛生責任者の講習が免除になる - 日商簿記3級
お金の流れを管理しやすくなる - バリスタ資格
コーヒーの専門知識や技術をアピールできる
これらは「信頼性の向上」や「自分の強みの証明」に役立ちますが、必須ではないため余裕があれば検討してみましょう。
資格や手続きは一見むずかしく見えますが、最初に必ず押さえるべきは食品衛生責任者と飲食店営業許可の2つです。
ここさえクリアすれば、開業への大きな一歩を踏み出せます。その後は、店舗の規模やメニュー、営業時間に合わせて追加で必要なものを整えていけば大丈夫です。
カフェ開業にかかるお金はどのくらい?
カフェの開業費用は、店舗の立地や規模、物件の状態によって大きく変わります。
小さなカフェでも、一般的には500万円〜1,000万円程度は必要とされるのが目安です。特に、家賃10万円・10坪程度の店舗を想定した場合、500万〜900万円ほどの初期費用がかかるケースが多いといわれています。
参考:日本政策金融公庫総合研究所「2023年新規開業実態調査」(2023年11月)
ここでは、代表的な初期費用の内訳を整理しました。
開業資金(初期費用)の内訳
| 費用名 | 内容 | 想定費用(10坪程度) |
| 物件取得費 | 敷金・礼金、仲介手数料、保証金など。家賃の数か月〜1年分を預ける場合もあります。 | 約120万〜150万円 |
| 設計・内装工事費 | 天井・壁・床の工事や、水道・ガス・電気の配線。居抜き物件なら大幅に抑えられます。 | 約20万〜 |
| 設備・備品費 | 厨房設備、コーヒーマシン、冷蔵庫、テーブルや椅子、食器など。 | 設備:約200万〜250万備品:約30万〜50万円 |
| 広告宣伝費 | 看板やチラシ、Webサイト制作、グルメサイトへの掲載など。 | 約20万〜50万円 |
合計目安:390万〜550万円程度
表の金額はあくまで目安で、こだわりや物件の状態によって大きく変動します。
特に「居抜き物件を活用できるかどうか」は費用に大きく影響するポイントです。
初期費用だけに注目しがちですが、開業後は家賃や光熱費、人件費などのランニングコストもかかるため、余裕を持った資金計画が欠かせません。
いきなり店舗を持たなくても始められる方法
カフェを開業したいと思っても、「いきなり数百万円の初期費用を準備するのは不安」という方も多いでしょう。
実は、必ずしも最初から独立した店舗を構える必要はありません。
小さく試しながら始められるスタイルがいくつかあり、初期投資を抑えつつ経験を積むことができます。
ここでは代表的な方法をご紹介します。
キッチンカー(移動式カフェ)
車両を使って移動販売を行うスタイルです。
- メリット:物件取得費や内装費が不要で、出店場所を選べば集客力が高い。少人数で運営できるため人件費も抑えやすい
- デメリット:車両の購入費や維持費、駐車場代などのコストがかかる。スペースが限られるため提供できるメニューが制限されやすい
間借り(レンタルカフェ・シェアカフェ)
既存の店舗の空き時間やスペースを借りて営業する方法です。
- メリット:家賃や初期費用が大幅に抑えられ、厨房設備をすぐに利用できる。既存客に知ってもらえる可能性もある
- デメリット:営業時間や曜日が制限される。内装や設備を自由に変えにくい
自宅開業型カフェ
自宅の一部を改装して営業するスタイルです。
- メリット:新規に物件を借りる必要がなく、固定費を大きく削減できる
- デメリット:生活空間と営業スペースを区切る必要があり、衛生・防火基準を満たす改装が必要。立地によっては集客が難しい
テイクアウト専門カフェ
店内席を持たず、持ち帰りを中心にする方法です。
- メリット:小規模スペースで開業でき、初期投資を抑えられる
- デメリット:ゆったりと店内で過ごしたい顧客層は取り込めない
これらの方法はいずれも「低リスクで始められる」点が共通しています。
また、最近では、キッチンカーや間借りカフェの事例をSNSで発信し、ファンを増やしてから実店舗に移行するケースも多く見られます。
いきなり店舗を構えるのには抵抗がある場合、まずは小さくスタートし、自分のコンセプトや運営スタイルを試してみるのも賢い選択肢と言えるでしょう。
夢のカフェ開業へ、最初の一歩を踏み出そう
カフェを開業するには、コンセプトの整理・必要な資格や手続き・資金計画といったステップを一つずつ踏んでいくことが大切です。
初期費用は500万〜1,000万円が目安ですが、居抜き物件の活用や小さなスタイルからの挑戦によって負担を抑えることも可能です。
また、キッチンカーや間借りカフェなど、いきなり店舗を持たなくても始められる方法もあります。こうした手段を通じて経験やファンを積み重ねてから、本格的な独立につなげるのも現実的な選択肢です。
カフェ開業は「夢」だけでは続けられませんが、堅実な準備をすれば「現実」として形にできます。
まずは小さな一歩から、自分のカフェ像を具体的に描き、行動に移してみましょう。
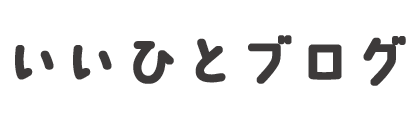
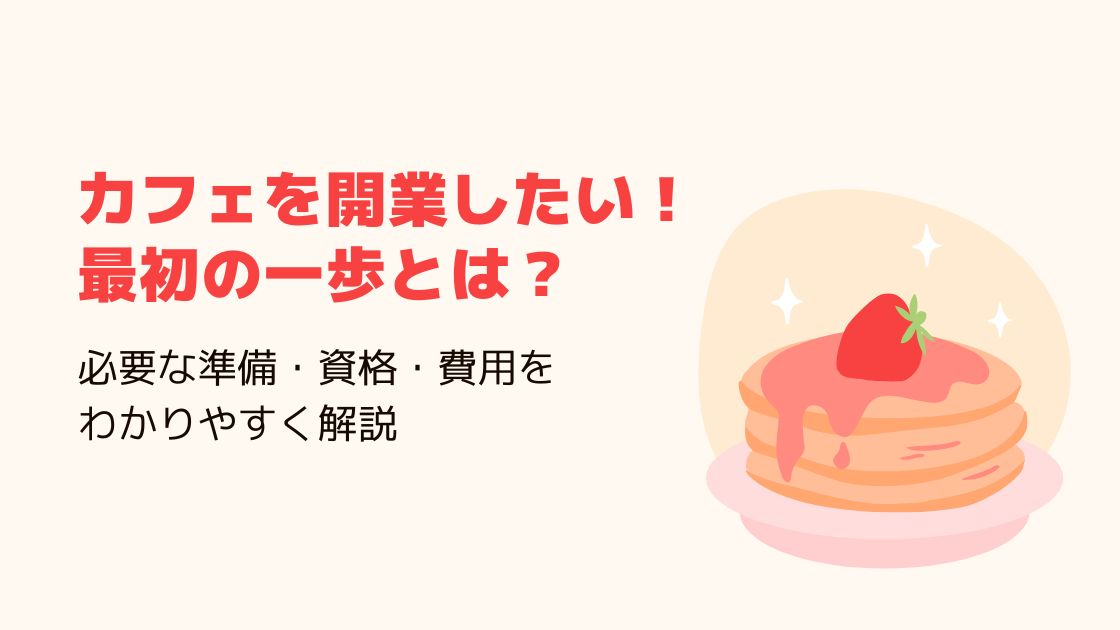



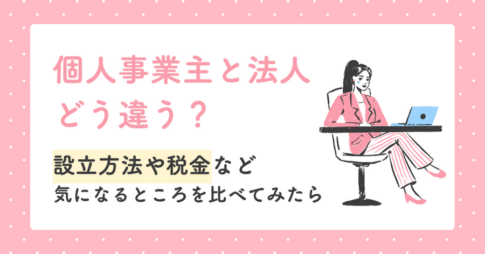

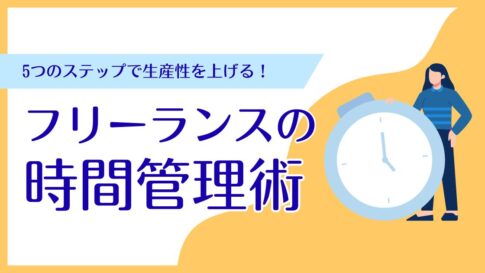
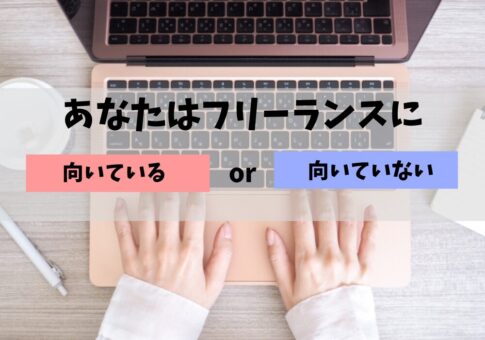


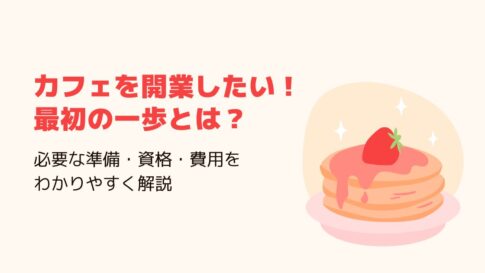












コメントを残す