日本の多くの地域が直面している、人口の減少や働き手不足。
こうした課題を乗り越え、地域を元気にするための国の大きなプロジェクトが「地方創生」です。
2025年、この取り組みが新しいステージへと進みました。
それが、令和7年6月13日に政府が閣議決定した「地方創生2.0」です。
この記事では「地方創生2.0」について、その基本的な考え方から具体的な支援策まで、わかりやすく解説します。
「地方創生2.0」とは?
「地方創生2.0」と言うからには、その前身(1.0)がありました。
まずは、1.0の反省点と、なぜ新しいステージへ移行する必要があったのかを見ていきましょう。
地方創生1.0の課題と「2.0」へのアップデート
これまでの地方創生(1.0)では、主に「東京一極集中」の問題を解決し、都市部から地方へ人々が移り住むことを目標に進められてきました。
様々な支援策が打ち出されたもののその効果は十分ではなく、特に若い世代や女性の都市部への流出を止めるには至りませんでした。
その背景には、
- 移住先で魅力的な仕事を探すことが難しい
- 女性が働きやすい環境が整っていない
といった課題があったとされています。
そこで「地方創生2.0」では、考え方を大きくアップデート。
人口減少と言う避けられない現実を前提とした上で、「今いる人々とこれから関わる人々で、豊かで持続可能な地域を作る」というアプローチに変わりました。
無理に人口を増やすことを目指すのではなく、それぞれの地域が自立して成長し、誰もが心豊かに暮らせる社会を目指す。
それが「地方創生2.0」の核となる考え方です。
「2.0」が目指す「強い経済」と「豊かな生活環境」
「地方創生2.0」が描くビジョンは、大きく分けて「強い経済」と「豊かな生活環境」です。
- 強い経済とは?
企業を誘致し、それぞれの地域が持つ強み(自然、伝統的な産業や文化、食材など)を活かして、強い経済基盤を築くことを目指します。 - 豊かな生活環境とは?
経済的な豊かさだけでなく、住民が安心して、地域に誇りを持ちながら暮らせる環境作りを目指します。
特に、若者や女性が「ここに住みたい」「ここで働きたい」と思えるような地域づくりに力を入れ、東京圏から地方への人の流れを今の2倍にすることを目標に掲げています。
地方創生2.0を支える「五つの柱」
では、具体的にどのような方法で「強い経済」と「豊かな生活環境」を実現するのでしょうか。
その計画は、次の「五つの柱」を中心に進められます。
①安心して働き、暮らせる「生活環境」づくり
柱の一つ目は、地方に住む人々が、日々の暮らしと仕事に安心感とやりがいを持てる環境づくりです。
特に、若者や女性が「ここでキャリアを築きたい」と思えるような魅力的な職場を増やしたり、女性がもっと活躍しやすくなるような支援に力を入れます。
また、人口減少が進む地域では、住民の生活を維持するために、閉校になった学校や郵便局などの既存施設を「コミュニティ・ハブ」として、交流施設や行政サービスの代行拠点にする整備が進められています。
②地域の資源を活かす「新しいビジネス」の創出
柱の二つ目は、それぞれの地域が持つ独自の資源を活かして、新しいビジネスやサービスを生み出す取り組みです。
▼新しいビジネス例
- 食・農業
地元でしか採れない希少な果物を使い、有名パティシエと高級スイーツを開発・ECサイトで全国販売する。 - 伝統産業
伝統の織物を、現代の有名デザイナーが監修し、ファッションブランドとして立ち上げる。 - 文化・スポーツ
美しい景観を活かし国際的なサイクリング大会やアートイベントを誘致する。
このように、地域の資源に新しいアイデアや技術を結合させることで付加価値を高め、地方経済を活性化します。
③都市から地方へ「人や企業」の流れを後押し
柱の三つ目は、都市部にある企業が本社機能を地方に移しやすくなるよう、税負担を軽くするなどの支援策です。
また、個人が地方へ移住しやすくなるためのサポートも拡充します。
これにより、都市部の企業や人材が地方へ移り、地域経済の新しい担い手となることが期待されます。
④「AI・デジタル技術」で地方の暮らしを便利に
柱の四つ目は、AIやドローンといった最新技術を活用して、地方が抱える課題を解決し、暮らしの質を向上させます。
▼AI・デジタル技術の活用例
- 山間部や離島に住む高齢者へ、ドローンで薬や食料品を届ける。
- バスの路線が廃止された地域で、AIを活用した乗り合いの自動運転車を走らせる。
- AIが観光客のデータを分析し、その地域に最適な新しい観光ルートを提案する。
こうしたデジタル技術を取り入れることで、地方は「最先端の技術で快適に暮らせる場所」へと変化する可能性があります。
⑤県境を越えた「広域連携」
柱の五つ目は、一つの市町村や都道府県だけで課題に取り組むのではなく、近隣の地域が協力し合う「広域連携」に取り組むことです。
例えば、複数の県にまたがる観光地が一体となって「広域観光ルート」を開発したり、共同でインフラを管理したりすることで、より効率的な地域づくりを目指します。
参考:首相官邸「石破内閣の主要政策 02/地方創生2.0の推進」
【地方移住希望者はチェック!】政府の移住支援策
「地方創生2.0」には、今後移住を考えている人にとって見逃せない、具体的な支援策がたくさん盛り込まれています。
特徴的なのは、単に住むことだけを応援するのではなく、様々な形で地域と関わる「関係人口」を増やすことに力を入れている点です。
①ふるさと住民登録制度
「いつかは地元に貢献したいけど、今は都市部で働いている」「好きな地域があるけど、移住はまだ考えられない」そんな人のための新しい制度が「ふるさと住民登録制度」です。
実際に住んでいなくても、その地域に「ふるさと住民」として登録することで、一住民のように地域の担い手として関わることができます。
また、登録者には地域の最新ニュースのメルマガ、特典品、協賛店でのサービスなどが検討されています。
これにより、都市部にいながらでも地域を応援でき、将来的な移住先候補にもなり得るでしょう。
②若者・女性を手厚くサポート
若者や女性の移住・定住を後押しするため、政府はさまざまな支援策を展開しています。
働きがいと柔軟な働き方を両立できる職場づくりや、女性の起業支援、ふるさとワーキングホリデーによる地域体験、高校生の「地域留学」など、移住前から地方とつながる仕組みが整備されています。
また、結婚・出産・子育てを支える環境整備も進められており、ライフステージの変化に応じた暮らし方ができます。
③「二地域居住」という新しいライフスタイルを促進
「平日は東京で仕事をして、週末は自然豊かな地方の家で過ごす」といった「二地域居住」というライフスタイルを促進する支援が検討されています。
「二地域居住」を検討している人に向けて、地方での住居の確保を支援したり、お試しで滞在できる拠点を増やしたりする取り組みが進められます。
④税金の優遇や補助金も強化
移住希望者への住宅補助や、税制優遇がさらに拡充される予定です。
企業の本社機能移転を促す「地方拠点強化税制」や、後継者不足に対応する「事業承継税制」の見直しが進められています。
また、中堅・中小企業の成長投資に向けた補助金や、地域企業への専門人材活用補助なども強化されます。
移住者・企業の双方を多方面から支援する施策が展開されます。
「地方創生2.0」が描く、これからの日本のかたち
人口減少や労働力不足といった課題は、今や一部の地方だけでなく日本全体が直面する現実です。
「地方創生2.0」は、その問題から目を背けるのではなく、地域の強みや人とのつながりを活かして、持続可能な社会をつくる試みです。
この記事で紹介した「地方創生2.0の五つの柱」や「移住希望者向けの支援策」は、その第一歩と言えます。
ぜひこの記事が、地方創生や地方移住について考えるきっかけになれば幸いです。
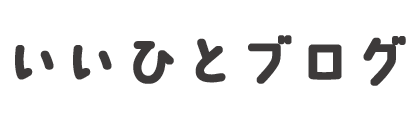








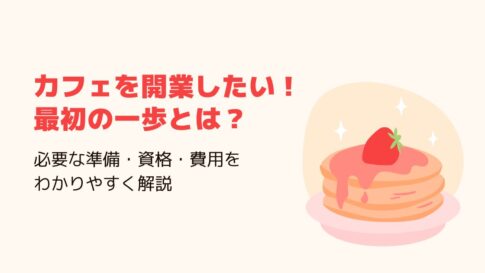











コメントを残す